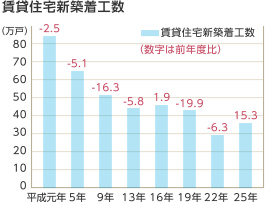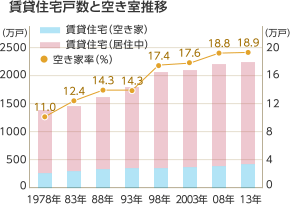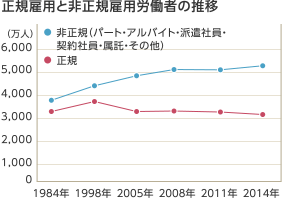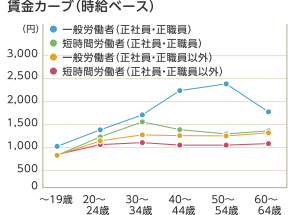オーナーさまへ
- 現在の賃貸情報
- 賃貸管理業界の問題点
- 賃貸管理に対する考え方
- これからの賃貸管理
現在の賃貸情報
2005年まで増加の一途をたどっていた人口が減少に転じ、出生数が死亡率を上回った現在の日本では、少子高齢化による人口減少社会に突入しています。2050年の人口は9000万人を割り込むとの予想が出されています。世帯数は、核家族化、離婚率の上昇、個人化の流れからしばらくは微増すると予測されますが、今後の人口の大幅な減少と連動して大きく減少していくことは確実です。
-
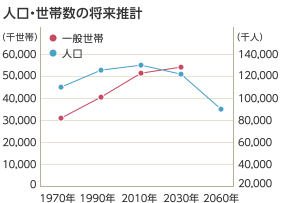
参考:総務省「国勢調査」
-
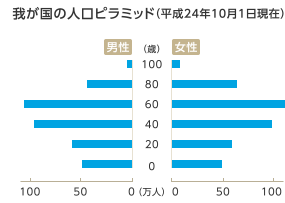
一方、新築賃貸住宅は建てられ続けており、このままではあきらかに供給過剰の状況が続き、2040年にはなんと空室率は40%前後になるという予測も出されています。空室率が上昇すれば、家賃は下落していくことになり、空室率が40%になれば家賃が40%下がります。オーナーさまの立場からすれば単純に収入が4割減少するという状況ですが、一方で固定資産税や借入金の金利等の経費はほとんど変わりません。
大競争時代に突入
借主が減り、貸し手が増える状況が続けば、当然賃貸市場での入居者獲得競争は激しさを増していくことになります。他の業界では市場競争は当たり前にあるものですが、わが国においては戦後長い間、住宅不足の時代が続いたこともあり賃貸市場において競争という概念はなかったのです。
しかし現在、貸し手同士での競争が必要なかった時代は終わり、これからは同エリア内での競争が激化し、オーナーさまの経営のやり方によって勝ち負けが決まってしまうという二極化現象が起こってきています。
資本主義経済では競争はあって当たり前の前提となる原理です。これまでの賃貸市場は例外とされてきましたが、今後は他の業界と同じように、競争市場になっていきます。そこで勝ち残っていくためには、競争の中で賃貸経営をしていくという意識を持ち、様々な工夫をしていかなければなりません。賃貸マンション経営においても、市場競争が前提にあるという認識を持ち、どのように生き残っていくかを考えて携わっていくことが必要な時代になってきたのです。利益をめぐる企業間の競争と同じ現象が、賃貸マンション経営の世界でも本格化しています。
-
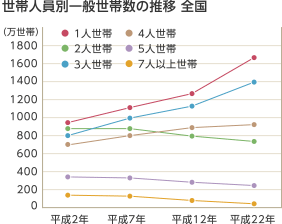
参考:総務省統計局ホームページ
-
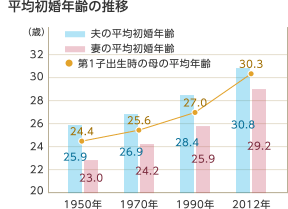
参考:厚生労働省「平成24年人口動態統計」
最大の敵は空室
需要と供給のバランスが変化し、激しい競争の時代に突入した賃貸市場では、賃貸マンション経営を行うオーナーさまにとって空室は最大の問題です。自分のマンションに入居者が入らないという状況は、売上が上がらないということであり死活問題です。
これからの賃貸マンション経営は、この空室をいかに埋めていくかという点に尽きます。しかし、あくまでも賃貸経営は利益の最大化を目指すことが必要であり、コストを無制限にかけたり単純に値下げをして空室を埋めるわけにはいきません。やはりできる限り費用をかけず適切な家賃設定を保ち、収支のバランスをとって空室を埋めることが、賃貸マンション経営の真髄でもあります。
これらをふまえ、今後の市場競争の中で利益を出して生き残っていくには、そのための専門知識とノウハウが不可欠です。賃貸経営では、不動産賃貸・売買等全般の知識や税務・法務の知識、建築・設備・工事全般の知識、ファイナンスの知識、マーケティング・入居者募集のスキル等、幅広く求められ、その道のプロでも一人で対応はせずチームで補完し合います。
-
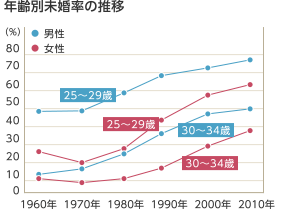
参考:総務省統計局「国勢調査報告」
-
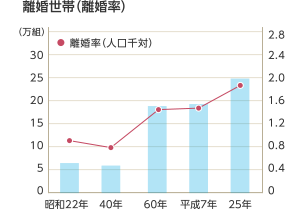
参考:厚生労働省「平成25年人口動態統計」
さらに競争社会においては、専門知識やノウハウはより早く高度化するため、少しでも多くそれらを身につけるよう努力しなければなりません。昨今インターネットの利用が生活に浸透した情報社会で、供給過剰の物件の中から少しでも好条件の部屋を探そうと、入居者の見る目はより厳しくなっています。時代は大きく変化しており、需要と供給のバランスが以前とは全く違います。住宅不足の時代からの考え方や方法をそのままにしていては、競争社会で生き残っていくことは相当に困難です。しかしながらこの業界において、実情を理解し対応しているオーナーさまや管理会社は未だ少数です。このような状況で、いち早く業界の変化を見抜き、一足早く対応を始めることで、競争社会で生き残っていくために圧倒的に有利となることがおわかりいただけるかと思います。
賃貸管理業界の問題点

賃貸市場の競争が激化し経営状況が厳しくなる一方、オーナーさまのほとんどが危機管理意識を持っていません。待っているだけで入居者が決まり、家賃が入って利益が出ていた賃貸経営の時代はすでに終わっているにもかかわらず、その実情を認識せず意識の脱却ができていないというのが根本的な問題です。
これを逆手に取れば、未だ多くの人が意識の低い状況であり、他の業界と比べるとまだ競争が厳しくなっていない今、いち早く現状を認識し行動を起こすオーナーさまは競争市場で優位に戦っていけるのです。
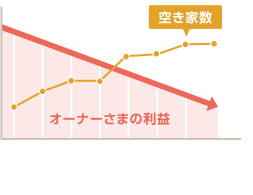
問題はオーナーさまが管理を委託する管理会社、ひいては賃貸管理業界自体の側にもあります。時代や市況が大きく変化しているにもかかわらず、ほとんどの管理会社の管理システムは住宅不足の時代の考え方をそのまま残しています。これからの住宅あまりの時代に合ったシステムを構築できていないことが最大の問題です。
現在の賃貸市場におけるほとんどの管理会社では自社で賃貸仲介店舗を持っており、そこで客付けをし入居者募集をしていますが、結論から言えば入居者募集をするに当たり、管理会社は自社で仲介店舗を持ってはいけないのです。
管理会社の役割は、オーナーさまの利益を最大化するための管理業務です。そのためには管理している物件に入居者を入れて空室を少なくすることが必須であり、自社で直接入居者を仲介することが本来の目的ではありません。管理会社が自社で客付けし仲介するための店舗を持ってしまうと、オーナーさまの利益を最大化するための管理業務と、仲介手数料を稼ぐという仲介の仕事が混在することになります。すると本来の目的であった管理業務の目的が達成しづらくなってしまうのです。
つまり自社で仲介店舗を持っていることが、オーナーさまの利益を最大化するために必要な管理業務を大きく制限してしまうことになるのです。こうしたシステムは、住宅不足が続き借主が空室よりも多い状況でこそ成り立つ構造であり、現在の状況に適したシステムではなくなっています。
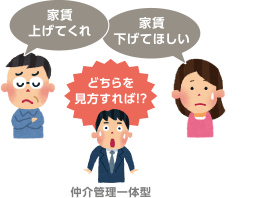
自社の仲介店舗を持つ管理会社は、その立ち位置が問題となります。「仲介管理一体型」の管理会社の基本的な問題点は、オーナーさまと入居者のどちらの立場に立って仕事をするのかという点で、立ち位置が曖昧になっているということです。管理会社はオーナーさまから管理料をもらった上で業務を遂行しているので、本来オーナーさまの立場に立って働くのがあるべき姿です。
しかしこうした「仲介管理一体型」の管理会社は、自社の仲介店舗を持っていることにより、極めて曖昧な立ち位置で仕事をすることが多くなっています。例えば空室を埋めようというとき、管理会社が自社の店舗で客付けして仲介し、オーナーさまと入居者の間に立つ立場として契約を結びます。このとき「仲介管理一体型」の管理会社は、入居者とオーナーさまの両方の利益について代弁する立場となっています。
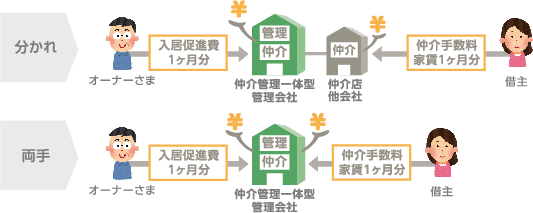
この場合、管理会社はオーナーさまからの管理料だけではなく、入居者からも仲介手数料を受け取っています。ですから入居者も「仲介管理一体型」の管理会社にとっては「お客さま」になり、入居者のためにオーナーさまに対して家賃の値下げ交渉をする場合も出てきます。この場合、オーナーさまの利益を減らすことで入居者の利益を確保することとなり、「仲介管理一体型」の管理会社は、オーナーさまの利益とは相反する立場、つまり利益相反の関係になってしまいます。
このことは日本の賃貸業の歴史的な背景が関係しています。元来日本の賃貸業は仲介から始まり、40年ほど前になってから管理業が生まれました。仲介から始まった賃貸業がその延長として管理業にも携わるようになったことから、入居者から仲介手数料を取り、オーナーさまから管理料を得るという業務形態が広く浸透しているのです。こうしてこの業態が業界の常識となっていきましたが、大空室時代を迎えた今、管理会社の立場の曖昧さやオーナーさまとの利益相反の関係が表面化するようになりました。
このような性質から「仲介管理一体型」の管理会社は、必ずしもオーナーさまの側に立ちその利益を最大化するために業務を行っているわけではなく、利益相反の関係の上で管理業を請け負っています。それに加え前述のように、多くの「仲介管理一体型」の管理会社は住宅不足時代だからこそ問題がなかった受け身の管理姿勢であることも大きな問題点です。このままでは管理会社とそれに委託する側のオーナーさまのどちらも、これからの競争が激化した賃貸市場で生き残っていくことは困難であると言えます。
1.入居促進費と仲介手数料の問題
図の場合の報酬配分は通常「分かれ」ということになり、お客さまを紹介する仲介(客付け)会社の売上は、入居者から得る家賃1ヶ月分の仲介手数料のみとなってしまいます。住宅不足の時代であれば、紹介できる物件があるだけでもよいという状況もありましたが、現在の大空室時代では紹介可能な物件は手に余るほどあります。こうした状況で賃貸仲介営業マンが、家賃1ヶ月分の仲介手数料しかもらえない他社の物件を優先して紹介するということはまずあり得ません。
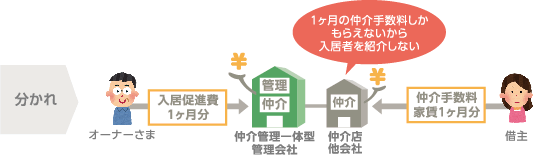
2.鍵の問題
賃貸仲介は現場のその一時で勝負しなればなりません。お客さまが来店してやりとりした後、その場で物件を案内することになります。この時、空室の鍵がどこにあるのかが問題になってきます。現場としてはできることならすぐに鍵を取り、迅速に空室を案内したいものです。
しかし「仲介管理一体型」の管理会社は、自社物件は自社で紹介することを前提にしており、基本的には自社で鍵を保管しています。すると仲介(客付け)会社は「仲介管理一体型」の管理会社の店舗に鍵を取りに行くという手間が掛かり、営業マンはこれを非常に嫌います。現場の細かい事情ではありますが、鍵の所在が部屋の案内のしやすさを左右するということも忘れてはいけない点です。ちなみに当社の管理物件の鍵についてはすべて現地で対応できるようにしていますので、各賃貸仲介の営業マンが物件にお客さまを案内しやすくなっています。
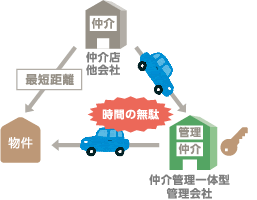
このように「仲介管理一体型」の管理会社では、自社以外の仲介会社からの客付け(仲介)は期待できないのが現状です。空室が長期化すれば、他社に頼って募集するということもありますが、これは自社の利益を最優先したやり方であって、オーナーさまに対しては利益を減らす行為となってしまいます。
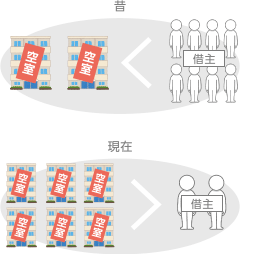
「仲介管理一体型」の管理会社の最大の特徴は、管理会社が賃貸仲介のために賃貸仲介店舗を持ち、自社で仲介(客付け)をすることです。これによって、管理会社がオーナーさま側と利益相反の関係になってしまうことはこれまで述べたとおりですが問題はそれだけではありません。
その性質上、入居者募集の間口が基本的にはその会社だけに狭められてしまうことも大きな問題です。借主が貸し手より多かった時代には、1社のみが客付けをしても満室にすることができました。しかし住宅が余っている現在では、1社が単独で満室にするのは困難になってきています。
一方で、一社で独占することには「仲介管理一体型」の管理会社の利益面で理由があり、その1つは入居促進費と仲介手数料収入の確保です。また集客のためにも意味があります。「仲介管理一体型」の管理会社は独占した部屋の情報を広告塔として利用し、その部屋を案内してほしい入居希望者はその仲介店舗に行くしかないという状況を作り出すことで集客につなげています。管理会社の役割は、オーナーさまの空室を埋めることが最優先にされるべきですが、管理会社の利益のためにオーナーさまの利益が削られる結果となっているのです。
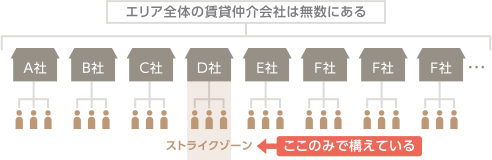
このように募集を1社で独占すれば、それだけ長い期間空室が続いてしまう可能性も高くなりますが、管理会社は空室期間を保証してくれるわけではありません。やはり「仲介管理一体型」の管理会社の業務形態では、オーナーさまの収益を減らしてしまうステムになっています。あまりに空室の期間が続けば、オーナーさまの手前、他社に情報を渡し募集することもありますが、入居促進費を一部抜くこともよくあり、あきらかに仲介店の利益を優先しているのです。
このような形態の賃貸管理会社が、現在でも業界の大勢を占めているのはなぜなのでしょうか。やはりその原因は、長く続いた住宅不足の時代にあります。日本では戦後からバブル崩壊までの期間、住宅不足が続き、店頭に多くの入居者が列をつくっているような状況でした。
圧倒的に需要が供給を上回っている、いわばオイルショックと同じような状態が続いたため、売るために試行錯誤することのない特殊な市場だったのです。
このために、仲介(客付け)と管理という相反する立場が1カ所の会社に存在するという状態でも、問題が表面化しませんでした。しかしながら今後は、何もしない受け身の賃貸経営では入居者は入ってくれません。今後は賃貸管理の立場や役割が明確化され、オーナーさまの利益になる仕組みや方法が必要とされてきているのです。
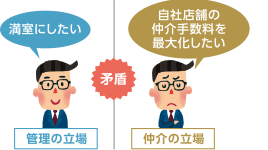
「仲介管理一体型」の管理会社で募集の間口がせまくなってしまうのはなぜでしょうか。それはこのシステム自体が矛盾しているということにあります。オーナーさまの利益のためである管理という立場と、仲介手数料を利益とする賃貸仲介という相反する立場を、「仲介管理一体型」の管理会社は同時に持っています。
管理とはオーナーさまの代理という立場から、満室にして家賃収入を最大限に保ち、オーナーさまの利益を最大化することが目的のはずです。そのためには、多くの仲介会社に依頼して広く募集することで少しでも多くの入居希望者を募り、部屋を案内することが必要です。管理会社の役割をメーカーに例えると、仲介会社の役割は小売店であり、できるだけ多くの小売店に販促活動を頼み自社商品を売ってもらわなければいけません。
当然オーナーさまにとっては、どの仲介会社が紹介してくれた入居希望者でも、入居審査に通りきちんと家賃を払ってくれる人であれば特に問題はありません。入居者がいないことが一番の問題です。しかし、賃貸仲介営業マンの立場を考えてみると違ってきます。
仲介会社の目的は売上となる仲介手数料や入居促進費であり、自社店舗を持っている以上、賃料等の固定費もかかることから、ほとんどの場合店舗や個人につきノルマが課されています。他社から仲介(客付け)をされた場合、仲介手数料は他社に入ってしまうため、できるだけ物件を他社には紹介せず、自社で独占しようということになります。さらに賃貸仲介営業マンは当然、「両手」を取ろうとします。店舗を持った業務形態である限り、こうしたことはどうしても避けられないのです。
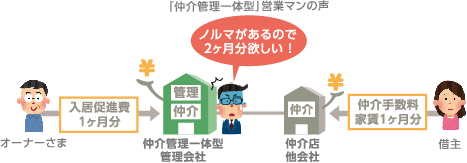
この状態は自社で販売店を持つメーカーと似ています。当然、全体の売上を最大化したいはずですが、自社の持つ販売店の売上を他の販売店よりも高くしたいのであれば、他の販売店での販売促進は制限されます。つまりメーカーとしては売上を最大化したいが、販売店としての売上も高く保ちたいという2つの異なった立場を一度に抱えてしまうために矛盾が生じています。これと同じ矛盾が「仲介管理一体型」の管理会社の一番の問題点です。
管理会社の目的は、オーナーさまの利益を最大化することですが、自社店舗があるために仲介手数料や入居促進費を最大化するという目的が加味され、本来の目的のための行動が制限されてしまうのです。
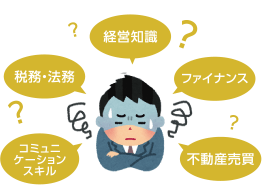
これからの時代、賃貸経営のプロとしてオーナーさまの代理という立場でその利益を最大化するには、賃貸市場での厳しい競争に勝ち残っていかなければなりません。今後必要とされる管理会社のあり方は、オーナーさまの利益を最大化するため、豊富な専門知識やノウハウを駆使して競争に勝ち続けることです。
しかし「仲介管理一体型」の管理会社の担当者は、残念ながら賃貸マンション経営の専門知識・ノウハウが不足してるのが実情です。また会社の仕組みそのものがそもそも賃貸の仲介業務から成り立っていることも大きな原因です。管理業務を含んだ賃貸仲介の営業と賃貸マンション経営というのは一見似ているようでもまったく別のものであり、賃貸仲介の営業マンは、賃貸マンション経営の経験、専門知識ともにほとんど触れていないのです。まして実際に賃貸マンションの経営をしている人はほぼいないと思われます。
ですから当然、オーナーさまの気持ちを理解することは難しく、これが問題点であると言えます。空室が続き不安を募らせるオーナーさまの気持ちに寄り添うことはなかなか困難でしょう。さらにオーナーさまの収支の状況を把握して業務を行うということもできません。また、会社の規模が大きければ大きいほど、担当者は「サラリーマン化」し、業務は分担化していきます。よく言えばスペシャリスト化していくわけですが、それはあくまでも管理業務の一部分のスキルでしかなく、幅広い経営のスキルは身につけられません。こうした背景も受け身の業務形態の一因であると言えます。
賃貸管理に対する考え方
利益の最大化とは
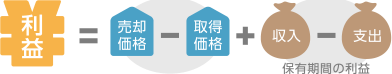
非常にシンプルですが、上図の「利益(最終利益,生涯キャッシュフロー)」を
最大化することです。
利益の最大化にこだわる理由
投資目的のオーナーさまに納得いただくためです。当社の管理物件のオーナーさまは、地主さまではなく投資家の方が多く、この点が多くの管理会社と根本的に違うところです。そのため、常に投資家の目線に立って業務を行うことが前提となっています。
投資家の方は、儲けるために収益物件を購入します。
投資家の方は、相続相続税の減税を目的として賃貸マンションを建築する地主さまとは大きく違います。減税が主目的で賃貸経営している方から管理業務を受託している会社の多くは、利益を積極的に求められていないため、一般的には業務内容が非常に曖昧なものになっている場合が多いです。一方、投資家の方々は利益を上げ儲からなければ意味がないと考えており、賃貸管理においても非常にシビアです。
シビアな要求に応えるため、日々より良い管理方式を追求してきました。
こうした投資目的のオーナーさまに応えるため、積極的にあらゆる手を打っていくのがツインライフのプロパティマネジメント(賃貸管理)であり、、その業務を委託される管理会社がその役割を担います。当社は管理会社として、「利益の最大化」のために様々な工夫をしながらプロパティマネジメント(賃貸管理)に取り組んでいます。オーナーさまの利益を最大化するには、物件の保有期間の利益だけでなく、売却までを含めてどれだけの利益を得られるかが重要です。
不動産投資の成功は管理(保有期間)で決まる。
売却は想定せず長期保有されるオーナーさまも多いため、当社は主に保有期間の利益の最大化に焦点を絞っています。保有期間においては、期間利益を最大化することが重要です。非常にシンプルなことですが、「収入を増やし、支出を減らす」ことを徹底的に行います。収入とは契約の賃料ではなく、家賃回収率までを含んでいます。
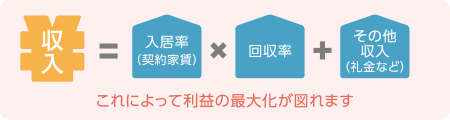
いかに入居率を高め、契約賃料を高めるかということ。つまり、いかに高い家賃で満室にするか。そして、滞納をなくし、家賃回収率を高めることも収入の最大化に直結します。さらに当然のことですが出ていくお金を最小限に抑えることも重要です。しかし現在、多くの賃貸管理会社で行われている賃貸管理の実態は、投資目的のオーナーさまの目指すところとは大きな矛盾があることも事実です。
例えば、「いかに高い家賃で満室にするか」というオーナーさまの希望に対し、今の業界の多くの管理会社は、自社の広告料収入を確保するために「1社のみで入居者募集活動」を行っています。これでは、目標となるのは管理会社の利益の最大化であって、オーナーさまの利益の最大化とは相反することになってしまいます。こうした管理会社の業務の実態は、オーナーさまに対して単純に募集賃料の減額とリフォーム工事をお願いするだけになっているのが実情で、オーナーさまの利益の最大化とは程遠いのが現状です。このような矛盾に満ちた業界構造にメスを入れ、オーナーさまの利益の最大化を実現する合理的な仕組みを構築したのが、ツインライフの賃貸管理システムです。
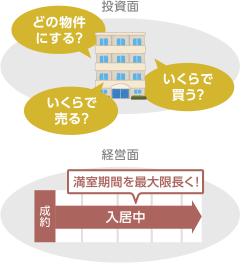
賃貸マンション事業の売上となる家賃収入は、ある程度の安定性が見込まれます。そのため飲食事業や建築業などの他事業と比べると、運営面での結果の差は小さくなります。そこで重要になるのは、”どの物件をいくらで買って、いくらで売るか”という初期段階での判断だと言えます。「適切な物件」を「適切な価格」で「適切な資金調達」で取得するという、取得の段階と売却の段階が、株や為替とも共通する、賃貸マンション事業の投資的な側面です。
株式投資であれば、株価は市場によって変動するので、利益を得られる時を見定めることしかできません。ところが不動産投資は一般の投資商品と異なり、自らの運用能力次第で、物件の保有期間の収益を高めることもできれば、逆に低くしてしまうこともあるのです。
「賃貸マンション事業」は、家賃収入を主な目的とした不動産投資ですから、その収入をどう得ていくかで収益が変わります。空室が続けば家賃収入が減りますが、その空室を減らせるかどうかは、オーナーさまの経営手腕にかかっています。「経営」という視点で、いかに満室を維持し、家賃収入を得ていくかが重要です。空室を減らすには、まずは満室になりやすい物件を取得するという「投資」の側面が重要です。しかし、どのような物件でも必ず退去は生じ、空室になる一定の期間はあるのですから、長年にわたり満室稼働させ、いかに収益を上げていくかという、経営的な手腕が投資の成功の鍵となります。
要するに、「賃貸マンション事業」では、物件の取得はスタートに過ぎません。具体的には、委託する管理会社の選択、空室が続いた際の募集賃料、敷金の設定、納税を考慮した大規模リフォームの時期など、経営的な視点を持った様々な判断が必要になってきます。こうした経営的側面を重視することで、成果につながるのが「賃貸マンション事業」だと言えます。
1.物件を保有する期間の利益

物件保有期間において、収入と支出の差を最大化する、つまりキャッシュフローを最大化することが重要です。株式や投資信託といった投資とは異なり、物件を保有している間の売上や利益が、「どう経営するか」によって大きく変わってくるのが賃貸経営の醍醐味と言えるでしょう。昨今の経済状況では、バブル期のように不動産の値上がりが続くことは期待できませんから、売却によって利益を得るのは、その手のプロ以外では難しいと言わざるを得ません。やはり、保有する物件からの利益を最大化することが重要だと言えるでしょう。
2.売却する際の利益
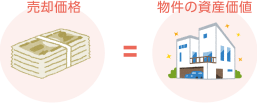
物件を高く売却するには、物件の資産価値を維持・向上させることが必須ですし、入居率も重要な要素となってきます。賃貸マンション事業は、長期にわたって保有することが前提ですが、売却を考慮に入れることも、利益確定のための出口戦略(運用方針)としては必要な場合があるでしょう。売却して更に高額な物件を購入するのが得策である場合や、相続で売却せざるを得ない状況も考えられます。どのタイミングでも良い条件で売却できるようにするには、「常物件の資産価値を高めていくこと」必要なのです。
ここで言う資産価値、つまりその物件がいくらで売れるかという市場価値は、基本的に「収益性」が決め手となります。家賃収入からの逆算(利回り)によって物件価格が決まりますから、年間収入が高ければ高いほど、物件の市場価値は高まります。
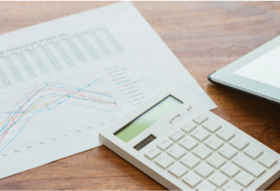
賃貸マンション経営においては、会社経営と同じように、「収入と支出のバランスを考えること」が必須です。賃貸マンション経営での主な収入とは家賃収入です。「家賃を高く得ること」「空室を減らして稼働率を上げること」の2つで、その収入を最大化するのが重要なポイントです。その前提となるしっかりとした管理運営の体制(入居者募集体制)を構築するには、「最大限効率的なリーシング活動」が重要です。
また支出に関しては、マンションの運営・維持のために必要な費用が主な支出となります。定期的に発生する費用としては、固定資産税、水道光熱費、税理士報酬、エレベーター維持費等があります。これらは「固定費」に相当し、基本的に入居率とは連動しません。これに加えて、「家賃収入を上げるために必要な支出」があり、これらは「変動費」に当たります。具体的には、入居者を入れるために賃貸仲介会社に支払う入居促進費や、リフォームする費用などです。家賃収入があっても、それ以上の出費が掛かってしまっていては、利益を出すことはできません。
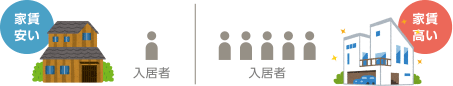
しかし、空室の多い昨今では、室内のクオリティを一定に保っていなければ、たとえ家賃を引き下げたとしても部屋は埋まらないでしょう。必要な室内リフォームの費用を渋ったばかりに空室が増え、収入が減ってさらにリフォームできない状況になるという「悪循環」に陥るケースも見受けられます。賃貸マンション経営では、支出を抑えて収入を高めるというバランスが、企業経営と同じように必要です。部屋あまりのこの時代に生き残っていくためには、こうした視点からの賃貸経営をしていくことが何よりも重要であると言えます。
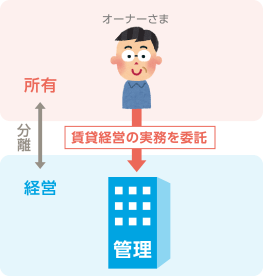
実態として、賃貸市場の空室率が高まっていることを考慮すれば、今後ますます専門知識やノウハウを持つプロ同士の入居者獲得競争が激しさを増すと予想されます。こうした状況では、オーナーさま自身では身につけきれない豊富な専門知識・ノウハウを持ち、オーナーさまの立場に立って、利益の最大化のために動いてくれる賃貸経営のプロに委託することが重要です。
これは「所有と経営の分離」と言い、一般の企業経営でも行われている手法です。賃貸経営を一般的な企業に当てはめてみると、オーナーさまは会社でいうところの株主にあたり、同時に最高意思決定者でもあるので社長としての役割も担います。ただしオーナーさま自身は賃貸経営の専門家ではないので、経営の実務はすべて専門家に委託し、本当に重要なポイントにおいて判断を下すことになります。もちろん専門家であれば誰でもよいというわけではなく、経営手腕を持ち自分の考え方を理解してくれる専門家を見つけることが必要です。経営を委託された管理会社は、経営の実務を仕事として働きますが、その目的はすべてオーナーさまの利益を最大化することにあります。
ツインライフではこの経営代理人としての品質を高めるため、社員が実際に賃貸マンションを所有し、自ら経営をしています。その実践の中で日々勉強し、その経験を業務に活かしています。オーナーさまと同じ立場に立つことで、実際の経営で出てくる悩みや不安なども共有することができます。このことからも賃貸マンションの管理業務では、「その管理会社の社員が実際にオーナーを経験していること」が非常に重要な点であり、大きな違いになると考えています。
一般的な企業においては、経営における専門家が経営を担い、専門家同士の競争が日々展開されています。今現在、所有と経営の分離した手法を取り専門知識を駆使した経営管理をすれば、周辺の賃貸物件との競争で圧倒的に有利な事業を展開することが可能になるのです。
これからの賃貸管理

プロパティマネジメントの目的
経営代行型(プロパティマネジメント)管理会社の行う業務はオーナーさまの代理業務であり、委託者であるオーナーさまが所有する物件からの最大収益(キャッシュフロー)を確保し、その不動産価値を最大化することが目的です。この目的を達成するために、プロパティマネジメントの管理会社は業態の中から徹底して利益相反となる行為(その疑いのある行為も含む)を排除しています。同時に、運用に透明性を持たせ、しっかりとした説明責任を持って業務にあたります。
また、従業員はこれらの内容を完全に理解し、業務に反映させることのできる実行力と能力、知識を持ち合わせていなければなりません。利益を最大化し、物件の稼働率を上げるための様々な手法を修得していますし、それを高いレベルで安定させる能力も重要です。例えば、月額賃料は常に近隣の相場より高い位置に設定できるように市場を調査・分析し、運用する物件をマネジメントしていきます。さらにリスクマネジメントも重要な業務で、物件の地域性や構造・設備、防犯上の問題、環境問題が発生する可能性、時間経過による危険度など、あらゆるリスクを将来に渡ってなくしていくように管理しなければいけません。
金融資産としての運用能力
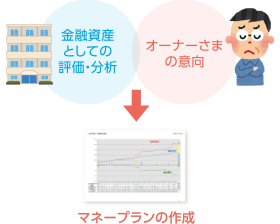
プロパティマネジメントによる不動産経営では、物件を金融資産としての観点から金融工学的に評価し、投資指数についても比較検証することができます。これらを基に、オーナーさまの意向を反映させながら運用計画書、マネープランを作成します。それに従って運用を実行していくことで、運用前、運用途中、将来にわたって不動産としての価値を最大化していくことができるのです。経営代行型の管理会社は、常に物件を金融資産として分析して問題点を発見、報告し、的確な解決策を提案します。そしてそれを反映させたマネジメントを行い、改善していくことで常に資産としての価値の最大化を図っていきます。
従来の賃貸管理では、このような業務がまったくと言っていいほど行われてきませんでした。先述の通り、日本ではこれらが求められる環境になかったので、これらの業務ができなくても何ら不思議ではないのですが、むしろ知らないことをオープンに自ら積極的に学び取り組む努力こそ、賃貸管理業界には求められているのです。プロパティマネジメントは手法を学べば学ぶほど、従来の賃貸管理との違いが判ります。それはきわめて合理的な不動産業界のグローバルスタンダードであり、携わる当社も自信と誇りを持って遂行できる、プロフェッショナルの手法であると言えます。
プロパティマネジメントと日本の賃貸管理
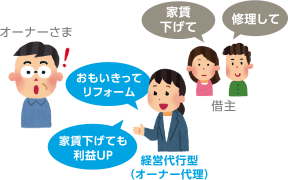
プロパティマネジメントは従来の賃貸管理とどう違うのでしょうか。管理という点では、基本的に行っている業務は表面上ほぼ変わりません。日本における賃貸業は基本的に「仲介業」から発展してきました。部屋を探す人に希望条件の物件を紹介し、仲介手数料をいただくという仕事です。
現在でも、「賃貸管理」業務をしていても主な収益が「仲介手数料」である会社は多くあります。仲介料はあくまで入居者からもらう収益であり、一方で「管理料」はオーナーさまからいただくものです。「管理会社」でありオーナーさまから管理料をもらっている限りは、オーナーさまの利益に貢献しなければなりません。「仲介」と「管理」はその立場が違うのです。
例えば「解約」の際、仲介の立場であれば入居者の解約は潜在的には歓迎すべきことになります。再度仲介手数料を稼ぐことができるのですから、積極的に解約を抑止しようという意識は起こらないものです。解約の抑止について、英語では「テナント・リテンション(Tenant Retention)」といい、プロパティマネジメントが確立しているアメリカにおいては、日本と違って大変重要視されています。解約が多ければ多いほど空室期間が発生し、さらに原状回復に掛かる費用もかさむので、損失は大きくなります。解約を少なくすることはオーナーさまの利益増に直結しますので、アメリカのプロパティマネジメントでは、常に「どうすれば入居者にもっと長く住んでもらえるか」を考えます。 この点が、仲介業から発展した日本の賃貸管理とアメリカの「プロパティマネジメント」の大きな違いです。不動産先進国のアメリカでは、そもそも居住系においては、「仲介手数料」を入居者からもらう習慣はありません。
「管理」の本当の意味とは
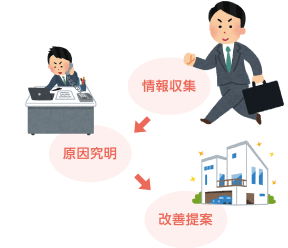
現在の「賃貸管理会社」の一般的な業務内容を確認してみます。まず、入居者を募集して、契約して、家賃を集金して、オーナーに送金して、クレームを対処して、物件の掃除・点検をして、退去立ち会いをする。それが、「管理会社」と、そう思っている方も多いことでしょう。それが「管理」ではないのか、と。
これでは、単に言われたことをやっているだけと言われてしまうかもしれません。しかし、「プロパティマネジメント」は違います。オーナーさまから管理料をいただいている以上、「オーナーさまの利益を最大化する」ための業務が必要です。
少しでも高い家賃で決め、空室・解約を減らし、日常的な運営コストを減らすことを常に意識して、管理・運営していかなければなりません。仲介の立場であれば、築年数が古く長期間空室が埋まらなければ家賃を下げる提案をするでしょう。この対策は即効性はありますが、結局はオーナーさまの手取り収入を下げるだけです。
早く決まり仲介手数料は稼げましたが、オーナーさまの利益より管理会社の売上を優先していることにならないでしょうか?「物件が古くなってきているのだから仕方がない」と思った方は、単なる「仲介」の方です。「マネジメント」の発想の方は、「物件力」そのものにおいて、いかに他の物件との競争力において見劣りしないものにするか、募集の戦略においても常に新しい方法を模索し、運営上の差別化についても追求します。空室問題を解決するには様々な手法があるのです。
「物件力」をつけるためには、再投資も考えなければなりません。再投資額に見合う家賃を回収できれば、最終的な手取り賃料が下がることがないわけです。そのためには、ローンを組む場合もあるためファイナンスの知識も必要です。その再投資が、収益とローンの返済との関係において、どういう意味を持っているか、すなわち「投資分析」もできなければなりません。
集客力を高めるための手段は、5万円のシャワートイレを設置するだけのことかもしれません。それとも2,000万円の「資本的支出」、または2億円をかけて新築物件への建て替えかもしれません。再投資することによって、オーナーさまの収益が現状より上がるというビジョンが描けることが肝要です。投資額の大小はありますが、額が違うだけで、本質的には、「プロパティマネジメント」になります。
「マネジメント」という言葉は、単純に日本語訳すると「管理」と訳されるかもしれませんが、これは正確ではありません。この「マネジメント(management)」には「経営」という意味が含まれています。「経営コンサルタント」の英訳は「Management Consultant」と言いますが、これはただ「管理」するということではなく、「経営的に管理する」という意味があるのです。
「プロパティマネジメント」は「収益物件の経営代行」と言い換えることができるでしょう。預かった物件の「経営」を任されているのがプロパティマネジメントであり、よって利益を維持しさらに成長させていかなければなりません。家賃の下落や空室期間の長期化が発生したとき、オーナーさまの利益は減少します。その際、他業界と同じように「情報収集し、原因を探り、問題点を発見し、対策を練って実行する」といった対応をするのが経営代行というものです。対策案の提案をできること、つまり改善提案をすることが従来の「賃貸管理」と「プロパティマネジメント」の違いだと言えます。
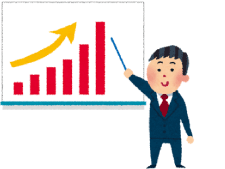
経営代行型(プロパティマネジメント)会社および担当者(従業員)の役割は、オーナーさまの利益の最大化を目的として業務にあたることです。オーナーさまに代わって経営を行い、利益を最大限引き出すことを目指します。
オーナーさまの利益を最大化するため、「物件保有期間中の収入を最大化し、支出を最小化することで保有期間におけるキャッシュフローを最大化し、売却する場合にはできるだけ高く売れるように計画し実行する」ことが必要です。またオーナーさまの状況を常に把握しそれに応じて適切な提案をしていきます。オーナーさまの経営を請け負っているので、その収支状況や資産状況(BS、PL、キャッシュフロー)を把握することは必須であり、会社の経営を把握することと同じです。自分の経営状況を把握せずに、経営にあたることはできません。
具体的には、オーナーさまの確定申告や決算の内容を把握し、利益が多く見込めそうであれば、ポンプの取り替えなど近い将来必要になる修繕を提案します。こうした工事は一括で費用計上できるように実施し、節税を図ります。こうした対応は、担当者に税務的な知識があってこそできるものです。また、毎月の金融機関への返済額も把握し、たとえば修繕費などの支出がかさむ月はその支払いを来月に延ばすなど、返済額との兼ね合いで調節するようにします。
こういった細かな対応により、オーナーさまのキャッシュフローは安定させることができます。経営代行型管理会社の役割は、あくまでもオーナーさまの経営代行であることを常に前提として業務に取り組んでいきます。
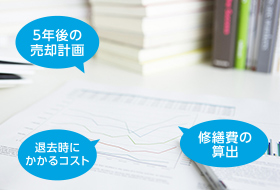
経営代行にあたっては、オーナーさまの物件に応じた事業計画を確認しておき、その計画に沿った提案・運営を実施していきます。一般の企業でも、5年後に売上をいくらにしてこれだけの利益を上げるといったように必ず事業計画(経営計画)を立て、それに則って経営を行います。賃貸経営も全く同じで、今ある物件を持ち続けるつもりなのか、あるいは数年後に売却を検討しつつ保有するのかでは、管理方針は大きく違ってきます。
例えば、5年後に更地にして売却を考えている物件があるとします。外壁が古くなりそろそろ修繕が必要だという状況だとすると、5年後の売却が決まっていれば、できる限りコストをかけない塗装工事を提案することができます。半永久的に保有する予定の物件であれば、きちんとした塗装工事が望まれますが、5年後更地にすることを考えればコストを圧縮するのが適切な判断となります。
また、5年後に取り壊し更地にして売却することが決まっているのなら、その時期にあわせて入居者の退去についても考えておかなければなりません。その場合、普通借家契約で入居者との契約を結んでいると、退去してもらう際に多額の費用がかかります。そのため必ず定期借家契約で入居者との契約を結ぶようにしておきます。
このように、管理業務においては、将来を見据えた事業方針をオーナーさまと管理会社が常に共有し、それに沿った対応をしていくことが重要です。同じ物件で同じ問題が起こっても、物件の今後の事業方針によっては、その対応方法が大きく変わることがあるからです。このように、起こった現象に対し単純な判断をするのではなく、その時々で柔軟な対応をしていくことが「管理」というものであり、オーナーさまの事業方針に応じて、能動的に利益の最大化のため行動することが何より重要なのです。
今後の賃貸市場は、オーナーさまを代行する賃貸経営の専門家(プロ)同士の競争になることが予想されます。裁判が当事者を代弁する弁護士同士の戦いであるのと同じで、高い専門知識・ノウハウを持った賃貸経営代行管理会社同士が本格的な競争を繰り広げていくことになります。同じエリア内でマンション同士の入居者の奪い合いが激化する獲得競争でしょう。
そして管理会社と仲介会社の役割が明確となり、管理会社は経営に特化、仲介会社は客付けに特化するというように分化が進むことが予想されます。あるいはそうならなければ、これからの競争市場においてオーナーさまも管理会社も生き残っていくことは困難でしょう。
こうした競争は他の業界ではすでに当たり前のことであり、熾烈なお客さま獲得競争が日々繰り広げられています。これまでの賃貸市場では、住宅不足の時代が長く続き、競争とは無縁の時代が長く続いたために、賃貸経営の知識・ノウハウのない方でも賃貸マンション経営に携わることができました。しかしそれは今まで賃貸市場が例外であったからできたことであり、これからの状況はまったく変わってきています。
オーナーさまにとってこれからの選択肢は大きく分けて2つです。1つ目は、オーナーさま自身で専門知識とノウハウを積み重ね、プロとしての専門性を身につけた上で賃貸市場での競争に挑んでいくというもの。2つ目は、自分の利益を最大化してくれる賃貸経営の専門家(経営代行型管理会社)に経営を委託することです。今現在ではまだ賃貸管理業界の競争市場は成熟していません。今このタイミングで行動すれば、確実に賃貸業界で生き残っていくためのアドバンテージを得られるでしょう。